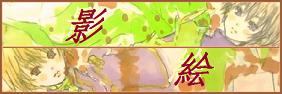自作小説メモ置き場。 話の序盤だけ書いているものを置きます。続きはおいおい別の場所で書く予定です。 ※未熟ではありますが著作権を放棄しておりません。 著作権に関わる行為は固くお断り致します。 どうぞよろしくお願い致します。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
第零話
僕が出会った一人の女性の話をしましょう
彼女は一人きりで生きていました
不思議なことです
周りにたくさんの友達が
彼女を想ってくれる両親が
ちゃあんといるのに
彼女は絶対に一人だったのです
彼女は僕に言いました
『旅人さん、旅人さん
わたし子供がほしいの
わたしだけの子供がほしいのよ』
『どうしてだい?』
僕はそっとたずねました
変なことを言うなあと思ったからです
彼女は答えました
『だってわたしにちゃあんと応えてくれるもの』
驚いたことに
彼女は子供という存在を
自分の所有物だと
思っていたのです
そしてその所有物とは彼女にとって
尽くしても尽くしても
絶対に裏切らないでくれる
必ず帰ってきてくれる
欲しい言葉をくれる
存在でした
奇妙なことです
彼女自身はそんな娘でもなかったのに
かわいそうな人です
僕はどうすることもできず
ただ彼女の頭をなでるしか
僕は自分の帽子をあげました
そして僕は
彼女のいる町を あとにしました
このお話には 続きがあります
何年かして
僕がまたその町を訪れると
彼女は僕と別れたその場所で
ずっとずっと僕の帽子を握りしめ
冷たくなっていました
ずっとずっと
僕の帽子を握りしめ
片時もそこを離れていなかったのです
僕は後悔しました
彼女を愛していたわけでは
いえ そう思っていたのに
ひどく胸が痛くて
僕は初めてその時気づいて
僕はそっと彼女を抱きしめました
しだいに腕の力が強くなって
僕は強く強く彼女を抱きしめて
どれくらいの時間が経ったでしょう
彼女の閉じられたまぶたの奥から
幾筋もの涙が頬をつたい
彼女はたしかに笑ったのです
その微笑みは
とてもきれいで
きれいで
急に吹いた一筋の風と共に
彼女の姿は消えていました
僕は僕の帽子をただただ
抱きしめていたのです
ただ一度でいい あの時
ただしっかりと抱きしめてあげていれば
よかったのに
僕は今更気づき ひどく後悔したのです
彼女は死ぬまで 自分を自分で抱きしめてあげるしか
なかったのだと
(旅人から知り合いへの手紙一部引用)
第一話
旅人が辿り着いたその町では
明く色とりどりのネオンサイトが
遠くからでもその町全体を
ぼんやりと浮きあがらせていました
スクーターをおしながら歩いていると
旅人は一人の少年に出会いました
少年は町のすみっこで
ちっぽけなうすっぺらの毛布1枚携えて
ただぼんやりと寝ころがっていたのです
『こんばんわ、ぼうや
何を見ているの?』
旅人は尋ねました
『こんばんわ、旅人さん
空を見ているんだよ』
少年は
朝も
昼も
夜も
毎日
毎月
毎年
くる日もくる日もこの同じ場所で
空を眺めていると言いました
最近は
何かを食べたり
飲んだりして
一瞬でも空から目を話す時間さえ
惜しいのだと言いました
『お腹すかないの?』
『すかないよ』
『楽しいんだね』
『うん、楽しいよ』
自分にとって 空は
永遠に続く映画で
しかもどの情景も同じものはなく
一度見逃したら二度と見ることはできない
尊いものなんだと少年は言いました
少年はさみしげに笑いました
『この町ではね
子供は迫害されるんだ
決められた仕事をこなす大人でないと
いじめられるんだ
そりゃあひどいものだよ
だからみんな早く大人になろうとするの
だから子供がこの町では
毎日毎日
次から次に
死んでいってしまうんだ
ねえ、旅人さん』
『なんだい』
旅人はこたえました
『旅人さんは大人なの?』
『どうだろうね』
旅人は少しだけ悲しそうに笑いました
『体は大きくなっちゃったけど
少なくとも大人だとは言えないな』
『そっか』
少年は空から目を離すことなく
にっこりしました
そして骨と皮だけになった
細く白い腕を
ゆっくりと上にあげ
まるで白いにごり水を垂らしたような
黒い空を指差しました
『人は死んだら星になるんだって
でも
星って
この町よりも
この世界よりも
ずっとずっと大きいものなんだって
遠い遠いところにあるから
小さく見えるだけなんだって
だったら
こんなちっぽけな姿でいるより
星になったほうがましなのに
なんで
死ぬのはこわいんだろうねえ』
旅人は
そっと少年の頭をなでました
そして旅人は
なんとなく
傍目には傷一つない少年の皮膚の下で
少年の心臓には
無数の引っ掻き傷やあざがあったことを
知ったのでした
旅人は空を見上げました
けれどどこを見わたしても
星なんて一つも見えやしません
旅人は少年に尋ねました
『僕の目は曇ってしまっているのかなあ
星は一つも見えないんだ
君には見えるかい?』
少年は首を横にふりました
『見えないよ、旅人さん
ネオンが明るすぎて
星を見えなくしちゃうんだ』
そして少年は
初めて空から目を離し
旅人の顔を
瞳を
見つめました
少年は微笑んで言いました
『大人達の作ったもの
大人達がいいと言ったもの
大人達を
見るくらいなら
目なんて必要ないと思ってた
大人達の作った音
大人達の作った文章
大人達の声
聞くくらいなら
耳なんていらなかった
この体も
大人達から出てきたものだから
でも
旅人さんと
お話できたから
こうして
お顔を見れたから
産んでもらえて
やっぱり、嬉しいな』
『ありがとう』
旅人は言いました
『さようなら、旅人さん
今晩はこの町に泊まっていくの?』
『さようなら、ぼうや
そうだね、そのつもりだよ』
少年はまた空を見ながらにっこりしました
『旅人さんの瞳の中に
ちいちゃな星を見つけたよ』
旅人はこの町に
三日間滞在しました
二日目の夜
何やら騒々しかったので
側を通っていく人に尋ねると
少年が一人
天に召されたということでした
その少年は
親の言うことにも
何に対しても
反発して
親不孝ばかり
していたということです
『ご両親はきっと、ちゃんと本当に
息子さんをとても愛していらっしゃったんでしょうね』
旅人は言いました
町人は大声で言いました
『ええそりゃあもうたいへんなかわいがりようで
あんなに大事にされて
あんなに恵まれて
なのに聞きわけがなくって
生きることに無関心で
勝手に自分を憐れがってねえ
あれじゃあ
親御さんがかわいそうでかわいそうで』
『おろかな子供ですね』
旅人は悲しげに微笑みました
『ええそうですとも、なんておろかな—』
『いえ、それとはまた違うんです』
旅人が言葉をさえぎり空を見上げると
町人は怪訝そうな顔をしていました
三日目の朝
旅人は町を発ちました
出発前に少しだけ
空を見上げました
空にはうっすらと
頭の欠けた白い月が
浮かんでいました
『昨日の夜は、星がきれいだったね』
旅人は
お月さまに向かって言いました
『おろかだね、とってもおろかだったね
でも僕は
おろか、って字は愛おしいって
愛らしいって
読むんだと
思ってるのだけれど』
旅人はスクーターのエンジンをふかしました
第弐話
旅人が辿り着いたその町では
ちょうど結婚式の最中でした
町中でお祝いをしていました
新郎新婦は
とても幸せそうに
白くて丸い馬車の中に
乗りこみました
また次の日も
そのまた次の日も
毎日誰かの結婚式が行われているのでした
また 空にはひんぱんに
コウノトリが
飛んできていました
『幸せな町なんですね』
旅人は微笑みました
『ええ そうですとも!』
町の人達は答えました
町を発つ日の朝
旅人は一人の娘さんに出会いました
『おはよう お嬢さん
きれいなドレスだね』
『おはよう 旅人さん
今日はね もうすぐ結婚式だから忙しいのよ』
娘さんは せっせと白いドレスの裾に
刺繍をほどこしていました
旅人はそっと娘さんの隣にすわって
しばらくその作業を
眺めていることにしました
不思議なことに娘さんは
小さなビオラの刺繍を
完成させてはほどき
また完成させてはほどきを
半ばとりつかれたように
くりかえしていました
『お嬢さんお嬢さん
作った刺繍が気に入らないの?』
『いいえ旅人さん
刺繍はできあがる度完璧よ』
旅人はしばらく目の前の小川をぼんやり見つめました
小さな蝶ちょがほろほろと飛びまわり
小鳥がささやかに鳴くので
とても優しい風が吹いていました
旅人はそれを見て
またにっこりと微笑んだのでした
『どうしていつも作り直しているの?』
『こわいからよ』
今日結婚するというその娘さんは
自分の着るそのドレスが
できあがってしまうことが
恐ろしいのだと言いました
『こわいの
こわいの
この町では
毎日結婚する人達がいるように
駄目になる夫婦も
たくさんいるのよ』
娘さんはようやく手を動かすのを
やめました
その頬を
幾筋もの涙が
つたいました
旅人は
娘さんの頭をそっと
なでてあげました
『きれいな髪だね
こんなかわいらしい娘さんだもの
きっとうまくいくよ』
旅人は言いました
娘さんは旅人をきっと睨みました
そしてまた
涙を流すのです
『まだ足りないのに
どうして
あたりまえに結婚して
あたりまえに妻になって
あたりまえに母親になって
あたりまえに終わらなければ いけないの
うまくいく保証だってないのに』
『どうして足りないの?』
旅人は聞きました
娘さんの横顔は
目はぱっちりとまんまるで
頬は薔薇のように赤くて
唇はもぎたての林檎のようにかわいらしく
まるでまだ幼い
女の子のようでした
『わからないの』
娘さんは答えました
『でもまだ 走り足りないの
ほら ねえ 見て
あそこの小川
あっちの野原
はだしで走り回って
ドレスなんかぐちゃぐちゃにして
どろだらけになって
おひさまの光いっぱいあびて
やりたいことはまだ
たっくさんあるのに
それあきらめて
ひきかえにして
大人になっても
幸せになれなかったら
悲しいわ
嫉妬するわ
わたしが産むかもしれない
子供たちには
まだそんな未来が
いっぱいあるのに』
旅人は尋ねました
『君のだんなさんになる人は
君のその気持ちを
わかってくれる人?』
『話したことなんてないわ』
娘さんはとげとげしく言いました
『話せるわけないわ
それだけで
もう十分に答えよ』
娘さんの中で
怒りがこみあげてくるのと同時に
何かが生まれてきているのを
旅人は見つけました
娘さんは また刺繍をはじめました
今度は それができあがっても
ほどき直したり しませんでした
旅人はそっと立ち上がり
側に生えていた白い花を一輪
娘さんの髪にさしてあげました
『さようなら お嬢さん
お幸せに』
『さようなら 旅人さん
あなたにも』
旅人が町の出口へスクーターを押しながら
歩いていると
一人の若者に 出会いました
若者は教会の前で
ただ立ちつくしていました
『こんにちは お兄さん
どうしたの』
『こんにちは 旅人さん
今日今から 結婚式なんだ』
若者はにかっと笑いました
その日だまりのような笑顔には
まだどこか愛らしい
少年のあどけなさが
残っていました
『あなたはその
娘さんが 好き?』
旅人が尋ねると
若者はりんごのように頬を染め
照れたように笑いました
『大切な人だと
思っているよ』
旅人もにっこり笑いました
『うまくいくといいね
きっと幸せになれるね』
そうだといいなあ と
若者は微笑みました
そしておもむろに言いました
『旅人さんは
薔薇の花を見たことあるかい』
旅人はにっこりと笑いました
若者も とてもとても柔らかな笑みを浮かべました
『薔薇は自分でいっぱいとげを持って
身を かたくなに守って
人を寄せつけないんだ
でも薔薇は咲いてもきれいだけど
蕾の時もとってもきれいなんだ
だから
見ていて飽きない
すっごく嬉しいんだ
憧れるんだ』
旅人は言いました
『痛くても けがしても
ちゃあんと手にとって 包みこんであげてね
ちゃあんと水はあげてね 蕾もきれいだけど
薔薇は咲いても きれいだから』
『ありがとう旅人さん
さようなら 気をつけて』
若者はにっこり笑っていいました
『ありがとうお兄さん
さようなら お幸せに』
去り際に旅人は思い出したように
優しく笑って 振り返って言いました
『さっき薔薇の蕾が
花開く瞬間を
初めて見たんですよ』
若者はきょとんとして
すぐにまた照れたように笑いながら
頭を掻いて 言いました
『ちぇっ 僕も 見たかったよ
まったく』
旅人がスクーターを走らせていると
鐘の音を
風が微かに 運んできてくれました
旅人は 少しだけ悲しそうに微笑んで
呟きました
『ほんとにちゃんと
しっかり抱きしめて
包みこんでやるんだよ
僕は
後悔したから』
旅人は 帽子を深く
かぶり直しました
(第弐話 おわり)
PR
不死鳥の玉座
第一章
第一話
アルフォンスは深いため息をついた。大理石の廊下には、彼のブーツのヒールの音が、静かに響いている。母と姉の長々しい説教からようやく解放され、今彼は酷いしかめ面で舌打ちをしながらのろのろと歩いていた。
毎度のことだが聞き飽きている。そしてこれまた毎度のことだが彼女らの説教には何の効果もない。
それを見てわかっていながらよくまあ飽きもせず変わり映えのしない小言を顔を真っ赤にして言えるのか、アルフォンスには彼女たちが気の毒にさえ思えてくる。
アルフォンスは非常に冷めた少年だった。名門貴族ロード家が半世紀近く待ち望んでいた、ようやく生まれた嫡子である。親戚総出で彼を教育したのは言うまで もない。全部で7人もいる姉もまた、どこの家にも負けない素晴らしい青年になるようにと、アルフォンスにとっては要らぬ世話をしてくれた。
12歳まで彼は、繊細ながらも非常に心やさしく素直な少年だった。だが彼は、当時唯一心を開いていた侍女のために、自分で紅茶を入れてみようとしたのだ。誤って熱湯をかぶり、左半身に大やけどを負った。それは侍女の責任とされた。
彼女は、首をはねられた。まだ17歳のうら若き少女であったというのに。
その出来事は幼いアルフォンスの心に暗い影を落とした。さらに、父からの愛情も失った。生々しく残ったやけどの跡に、父は顔をそむけた。まるで汚らわしい ものを見るかのように、冷たい視線を浴びせかけた。逆に母や姉は、アルフォンスをますます猫かわいがりするようになった。ありとあらゆることを身に着けさ せようとした。完璧が求められた。ロード家の中でも、アルフォンスの親子は白い目で見られるようになったからだ。
アルフォンスの中に、激しい憎 悪にも似たどす黒い感情が巣食うようになった。侍女の首をはねるように進言したのはほかでもないロード家の人間たちだった。アルフォンスは、この冷たい牢 獄のような家柄に、いつしか呼吸ができないような苦しさを感じて生きるようになっていた。
それでも人前ではあどけない笑顔を作り、かわいらしい声で応えた。決して、『期待されていない』振る舞いはしないように努めていた。それが次第に息苦しくなっていったのだ。アルフォンスの性格は、そういったものとは全く正反対のものとなってしまっていたからだ。
アルフォンスが初めて、救われた心地がしたのが、社交界デビューをはたした15歳の秋、貴族ソワンジュ家の嫡子ジョシュアとその妹ネシカと出会った時だった。
ジョシュアはかなり変わった少年だった。服装も独特だった。ひざ丈のゆったりとしたズボンにフリルをあしらったブラウス、上にはまるで教会の神父のような 上着をかぶっていて、手足の細さが際立っていた。アルフォンスより2歳も年上のくせに、まるで10歳そこらのあどけない少年の雰囲気をまとっていたから、 その舞踏会にはそぐわない恰好も、なぜかとても似合っていてかわいらしいとさえ思えた。分厚い本を2冊大事そうに抱え込み、ネシカのダンスを見届けるとそ そくさとすみっこへ走って、床に座り込んで本を夢中で読み始めた。アルフォンスはしかし、ジョシュアが気になって仕方がなかった。そっとそばに寄って行く と、ジョシュアはほんのしばらく顔をあげたが、にっこりと笑ってうなずいただけだった。アルフォンスはしばらく彼の隣りに座って、彼の読んでいる本を横か ら眺めていた。いつのまにかネシカもアルフォンスの隣りにしゃがみ込んで、にこにこしながら2人を眺めていた。
しばらくして、ものすごい剣幕でアルフォンスを呼び戻しに来た姉に捕まったが、それまでのわずかな静かな時間が、なぜか泣きたくなるくらい幸せに感じられた。
ロード家に帰りついた途端、アルフォンスは父と母から鞭で叩かれ叱られた。ソワンジュ家と関わったことが、彼らの気に触ったのだ。アルフォンスには、なぜ 怒られなければならないのかわからなかった。その理由を、誰も教えてはくれなかった。誰かに尋ねてみたり、調べさせたりするだけで、それはまた両親に伝わ り、同じようにぶたれた。
だがアルフォンスはすっかり家族に対する信頼をなくしてしまった。それまでどこにもなかった逃げ場の存在に、気づいて しまったことが、アルフォンスの忍耐力をそぎ取ってしまっていた。ここは僕の居場所じゃない。この家にはいたくない。出て行ってやる。そんな希望が日に日 に膨らみ、アルフォンスを興奮させていた。こんなに楽しい気持ちになったことは、今まで一度もなかった。
のたれ死んでもいい。とにかく、ロード家にしばられない、ただのアルフォンスになりたかった。親から与えられたアルフォンスという名前さえ、捨ててしまいたくなった。
社交界にも、もう行けなくなっていた。ソワンジュ家とは関わらないと同意するまで、外に出してはもらえなかった。アルフォンスはある時、たった一人で歩い て街に出た。明け方だった。窓から抜け出し、見張りのものに金を渡した。それでもどうせ家族に言いつけるに違いなかった。だとしても、少しでも時間を稼げ るなら、アルフォンスにとっては十分だった。
わざとマントをゴミ箱に突っ込み、汚くした。乞食のような格好をしていれば、すぐには見つからないだろう。アルフォンスはただ歩いた。どこに行けばいいのか分からない。何も知らないのだから。それでもいつかたどり着けると信じていた。
街にはソワンジュ家のうわさはあふれていた。精神異常者の家系だ、貴族社会ではうとまれており、裏社会にも通じているらしい、けれど、貧しい暮らしをして いる者に、食べ物を定期的に持ってきてくれる。寒くて凍えそうな夜には、当主が自ら街に下り、人々と同じ薄着をして、彼らと寄り添ってひと晩明かす。変 わってはいても、心はやさしいのだ。人々はそう言って穏やかな顔をした。おんぼろの屋敷に住んでいる。改築もせず、お金は街の人々に分け与え、貴族らしか らぬ食事で過ごしている。よそいき着は妹のためのドレス3着しか残っていない。
(続く)
Echoes~エコー~
第一部
第一章
一、蜂蜜みたい
そこは深い深い森の中。
一人の少女が、ふらふらとしながら彷徨っている。
少女は蜂蜜のような美しい深みのある金髪に、コスモスのような青みを帯びた淡紅色の瞳をしていた。
もう長いことまともなものを食べていない。おかげで視界はぼんやりとして、頭はずきずきと痛んでいた。腹は空いていたが、ここまで来ると疲労ばかりで何か食べ物を探そうという気力さえ湧いてくれない。
少女はとりあえず一本の木の根元に腰をおろして、まどろみ始めた。
糖分の欠乏している体は、すぐに眠りについてしまう。眠っている間が一番楽だった。目が覚めると酷く空腹を感じて、苦しくなる。立つと目眩もするし、本当に、そろそろこのままあの世へいきたいと、ぼんやりそんなことまで考えてしまっていた。
―苦しい。
ひくひく、と喉が震えた。少女は自分が幼子のようにみっともなく泣いていることに気付く。
自分でも、情けないと思った。一体自分はどれほどの命を勝手に奪っただろう。それでも死ぬことに自分で涙を流している。なんて自分勝手な生き物だろう。
少女は、異種族間のハーフだった。ハーフは何も珍しいことではない。けれどその中でも彼女は特殊だった。
普通異種族間の契りというのは同じくらいの力あるいは体格のある者同士で結ばれる。そうでなければならない。もしも母親と父親との間に能力や体格的な差異 がありすぎると、生まれてくる子供はその差分に苦しめられることになる。己の体の中で相反する力が拮抗し、その反動で内に溜まりに溜まった破壊的な力を衝 動的に外へ排出しなければ自己を保てなくなるのだ。
つまり、発作的に周囲を巻き込む力の大暴走を起こしてしまうことになる。
少女こそ、その類だった。
小人の類に入り、虫ほどの力しか持たない妖精の母親が、魔族と呼ばれる超能力を有する種族の中でも高位に位置する竜族(ドラゴン)の青年との間に設けた子供が彼女だった。
あまりにも開きすぎている力の差は、そのまま彼女の内で膨大なエネルギーとして溜まり、彼女を苦しめる。そして、彼女の意思とは関係なく、本能的に、周期的にそのエネルギーは爆発し、周囲を焼き尽くしてしまうのだ。
そのせいで、彼女は今まで罪もない人々をどれほど殺してしまったか、もう分からない。
けれどどうすることもできない。だから彼女はただ逃げていた。できるだけ遠くへ、誰も周りにいない世界へ、辿り着くため。
そのうち、この、終点も見えない深い森の中に迷い込んでしまったというわけだった。いつしか食べられるものすら見当たらなくなり、飢え死に寸前の状況に陥っている。
けれど少女は、それでも悪くない、とも思っていた。
ここで死ぬのも当然かもしれない。それだけの罪を自分は重ねてきたのだから。
それなのに、いざ死を目の前にすると、死にたくないという思いがわき上がってくることが情けなくて仕方がなかった。
一体どうしたらよかったというのだろう。
少女は、こらえきれず嗚咽を漏らした。こんな力が欲しかったわけじゃない。こんな思いをするために生まれたのなら、生まれてきたくなどなかった。
どうして母親は自分を産んだのだろう。何故ドラゴンと契りを結んだのだろう。
母親にぶつけたかった言葉は、ひとつもぶつけることができなかった。彼女は、胎児の持つ絶大な力のせいで、彼女を産む直前に息絶えたのだから。少女は死ん でしまった母親の腹から急いで取り出された。助かったのは彼女だけだ。少女は間もなく、自身の力で母親の生まれ育った妖精の村をも破壊してしまった。
「おかしいなあ。いい匂いがしたと思ったんだけど」
「だから、気のせいではありませんこと?こんなところに食べ物があるわけでもなし」
「あるいは、餌を呼び寄せる毒花の出す香の類かと思います」
「うわ…やめてよ、わたしは花の餌食になんかなりたくありませんわよ」
「俺だって御免こうむりたいです」
「煩いなあ。ちょっと黙っててよ。分からなくなるじゃない」
「…言っときますけれど、嗅覚と聴覚はまったくもって連動しませんわよ」
「いたいた痛いっ!!引っ張らないでよっ」
「え?って、引っ張ってなんかいません!!勝手にあなたが髪をわたしの服に絡ませてるだけでしょう!!」
「オレのせいじゃにゃいもん!!い痛っ」
少女ははた、と顔をあげた。
場にそぐわないような能天気な会話がどこからか聞こえてくる。
いつの間にか涙は止まってしまっていた。力が抜けて、少女はその場で呆けてしまう。がさがさ、と頭上で音がして、何かがぬっと少女の眼の前に影を作った。
「あれ」
影が呑気な声を出した。逆光でよく見えないが、少年の逆さの顔のようだ。そもそも少女は視界もかすんでいるから、よけいによくわからない。
「ねえ、こんなところに女の子がいるよっと」
少年はそのままくるっと体を空中で回転させて地上に降りてきた。続けて黒い影が三つ、ざざっと音を立てて上から降ってきた。
「どれどれ…ってこの子!!死にかけてるじゃありませんの!?」
少女らしき可愛らしい声が小さな悲鳴をあげた。
「見たところ、栄養失調ってところですね。この森に迷い込んだものの一般的な末路の図です」
淡々とした、抑揚のない少年らしき声が続いた。
「そ、そんなこと見れば分かりますわ!」
「というか助けてあげにゃいのー?」
「煩いわよバカ猫っ。何まともなこと言ってやった顔してますのっ」
「にゃっ!?にゃ、にゃにか文句でもあるのか!?」
「あー煩い煩い。喧嘩ならあっちでやってくれる?僕たちに被害の出ないところで」
最初に降りてきた少年が手をひらひらと振って言った。
薄い青緑色の、森のような色の髪をしているのだけはわかる。そして肌が目が覚めるほど白いことも。けれどそれ以上はかすんだ目ではよく見ることができない。
少年は少女の眼の前で手をひらひらとかざした。
「見えるー?」
少女は首を横に振った。
「ふーん…焦点あってないなあとは思ってはいたんだけど、ね。ねえヴィオ、この子目が見えない子なのかな」
「その可能性も確かにありますが、栄養失調が過ぎると視力に異常をきたすことがあります。その場合は栄養さえ取ればしばらくすると治るはずですが」
「なーる。何かとりあえず食べさせてあげる?あと何が残ってたっけ」
「ファビの缶詰があと三つ、フォトフの燻製が七枚、あと昨日採ったクレオの焼いたのがまだ五切れあったかと」
「…そろそろわたしたちの食糧源も危ないんじゃありません?」
「まあ、それもそうだけど。でもほら、見てよ、この子の髪。蜂蜜みたい。美味しそう。すごく美味しそう」
「…あなたが言うと洒落になりませんわ」
「にゃ…」
「ははははは。どういう意味かな?」
「まあ、蜂蜜みたいな色、というのは俺も同意です。美味しそうかどうかまではよくわかりませんけど」
「だよね。それにこの子、なんか甘いいい匂いがする」
少年がくんくん、と匂いを嗅いでいるのが分かった。少女は途端に恥ずかしくなってきた。
そもそもここ何日もこの森で彷徨っていたのだから、風呂にすら入れていない。少女は首をただ振った。
「…女の子の匂いを嗅ぐなんて変態なのにゃ…」
「煩い猫。何まともなこと言ってんだ猫のくせに」
「オ、オレ虎だもん…猫じゃにゃいもん…」
猫と呼ばれた幼い少年がべそをかいた。
「ヴィオ、クレオ寄こして」
ヴィオと呼ばれた黒髪の少年が背中に背負っていた荷物から何かを取り出す。焼いた魚のいい香りが少女の鼻をついた。動くのを忘れていた腹がまた活動を始めたのがわかった。少女はなんだか悲しくなって首を横に振った。
「い、いらない…わたしには、かまわないで、お願い」
「なぜ」
少女は言葉に詰まった。またじわりと涙が滲んできた。
「い、いいの。このままでいいの。このまま死なせてください。わたしは、死ななきゃだめなの」
「…随分悲しいことを言いますのね、この子」
淡紫色の髪をした少女が低い声で言った。
しばらく流れた沈黙を、最初の少年のくすくす笑いが破った。
少女は眼を見開いた。何故少年が楽しげに笑うのか理解ができなかった。
「へええ?死にたい、と。ふーん」
少年はなおもくすくす笑っている。
「あんた面白いね!」
少女は訳が分からなくて目を泳がせた。少年がにんまりと笑ったのがわかった。
「まあ、ほっとけば君は死ぬだろうね。ということで、ここからは僕たちが君の身柄を預からせてもらうことにします。いいよね?」
少年は振り返った。小さなため息が漏れた。
「まあ…やらかすだろうなとは思ってました」
「そうね…この人拾いものが趣味だし」
「い、いや…構わないで!わたしにかまわないで!」
少女は叫んだがかすれた声しか出なかった。
先の少年はきょとんとした顔で言った。
「え?だめだよ?僕君の髪の毛気に入っちゃったんだもの。蜂蜜みたいで美味しそう。このままみすみす逃しちゃうなんて、なんてもったいない」
少女は気が遠くなる想いがした。随分と横暴な少年に見つかってしまったらしい。
「で、ヴィオ、この子おぶってあげて?」
少年は首をちょこん、とかしげて見せた。黒髪の少年は溜め息をつきながら少女の傍に寄ってきた。
「…ご自分でおぶってあげる、という選択肢はないのかしら」
「だってーエリカ嬢。僕こんないたいけな子供だよ?つぶれちゃうよー」
「…その気になれば大人になれるでしょうあなたは」
ヴィオ、と呼ばれていた少年は少女を抱きかかえてたちあがった。
「あれーヴィオ!なにそれお姫様だっこ」
「…ですから、彼女は衰弱しているので変に負担をかけるよりもそのままの体勢のまま連れて行った方がいいかと判断しただけで」
ヴィオという少年は溜め息をつきながら言った。
その手から伝わる温もりは温かく優しくて、少女は意に反してまどろみ始めていた。
「ふふふ。嬉しいにゃー。可愛い女の子がまた仲間に増えるのにゃ」
「…こ…いつ、ガキになってもやっぱり女ったらしなのね…っ」
エリカ、と呼ばれた少女がうんざりしたように言った。
薄い青緑の髪の少年ももっとうんざりしたような声で言った。
「…成体になるとこんなもんじゃないしね…」
「エコー。お願いですから冥土に行くような表情にならないでください」
ヴィオが溜め息をつきながら言った。
「そもそもそんな彼を拾ったのもあなたでしょうが」
「…だってさ…フィグ見てたら…あれだよそう、『自分の父親を檻に入れてビシバシ躾けてやりたい気分になった』ってやつ」
エコーと呼ばれた少年は妙に黒い声で言った。
「フィグって呼ぶにゃ!!」
「煩い猫」
「ロン、あとでわたしの分のクレオ食べさせてあげますから機嫌直して」
エリカがため息交じりに言うと、銀髪の幼い少年は嬉しそうな声で喜んだ。
「わーいっ」
「眠ってていいですよ?」
ふと、ヴィオが少女がうとうとしているのに気付いて声をかけてきた。
「糖分が足りていないと眠くなるものですから。安心してください。落としはしませんから」
とてもぶっきらぼうだったが優しい声だった。
少女は抗うこともできずに、そのまま深い眠りに落ちていった。
二、面白い
ダニエリンが目を覚ますと、体中を幸せで満たしてくれるような、美味しそうな匂いが彼女を包んでくれていた。なんだかダニエリンは泣きたくなってしまった。
―食べたい。
そういう希望が出てきたことへの喜びと、悲しさと、恥ずかしさが彼女を苦しめた。
また、無意識にしゃくりあげていた。そんな彼女の横に、誰かが勢いよくしゃがみ込んだ。
はっと顔をあげると、淡い青緑色の柔らかな猫っ毛の少年が、にこっと笑っていた。
「あ、焦点あってるね。僕の顔見える?」
ダニエリンは自分でも驚いていた。いつの間にか、それでも普段よりはまだかすんでいるとはいえ、少年の顔が分かるほどまで視力が回復している。
「君がもう意識不明みたいになってたからね。ヴィオがずっと解放してくれてたんだよ。流動食作ってね、ずっと君の口に流し込んであげてたの。それはもう…甲斐甲斐しく口移しでっ」
「えっ…」
ダニエリンは絶句する。
「嘘八百並べないでください。流動食を作ったのも世話をしたのも確かに俺ですが口移しまではしていません」
ヴィオの少年らしいかすれ声が不機嫌そうに響いた。ヴィオはふっとダニエリンに笑いかけた。
「顔色もよくなったな。よかった」
「あれあれーなんかいい雰囲気だねっ。おにーさんはさっさと退散するね―」
「その花畑な思考を直していただくまではここにいていただきましょうかね?」
ヴィオが怒りにまみれた低い声で言って少年の襟首をつかんだ。
「まったく…ほんとにエコーはヴィオをからかうのが好きなんだから…」
エリカが苦笑する。そしてダニエリンの両頬をぱしん、と手で挟み打ちした。
「い痛っ!?」
「いいですこと?もう二度と、あんな哀しいことは言わないでください。分かりましたか?」
このまま死にたい、と言ったことだろうか、とダニエリンは思った。ダニエリンはエリカの金色の瞳の奥に真剣なものを感じ、半ば無意識にうなずいた。エリカは柔らかく微笑むと、エリカの頭を撫でくり回した。
最初はなんとなく嬉しい気もしたが、次第にエリカの瞳に宿ってきた何かを見て、ダニエリンは唖然とした。エリカは眼をハートにしてまくしたてた。
「で、ですわ…この子可愛いですわっ!!どうしましょうどうしましょう!!やっぱりここはフリルのいーっぱいついたドレスとか似合うと思いますの!!あ、でもミニも捨てがたいですわね!!どうしましょうかしらどうしましょうっ」
急に顔を真っ赤にして一人で悶え始めたエリカにダニエリンは茫然とした。
救いを求めるようにヴィオを見たが彼は眉間に指をあてて顔をそむけている。
「だよね?この子結構可愛いと思ったんだよね僕」
「はあ!?」
ダニエリンは思わず声をあげた。
エコーと呼ばれていた少年はじいっとダニエリンの顔を覗き込んだ。その男の子にしてはあまりにも整い綺麗すぎる顔に、ダニエリンは顔が紅潮するのがわかった。
薄いパールブルーの大きな瞳が、ものすごく神秘的で綺麗だ。
「うん、こんな綺麗な金髪初めて見たし、そもそもこんなコスモスみたいな目も初めてだ。すっごく綺麗。君もしかして妖精の血引いてるでしょ」
ダニエリンはびくり、と肩をはねさせた。なるべく答えたくない。けれどエコーの眼差しに勝てそうにもない。ダニエリンはあっけなく白旗をあげた。
「う、うん…」
「やっぱりね!!こんな美しい種族なんて、妖精と巨人族くらいしかいないよね!!ま、巨人族にはもう女の子はいないけど」
気のせいか、最後の言葉には何か刺が含まれていたような気がした。
「とはいえ、ね、君はヴィオのことどう思う?すっごく顔綺麗でしょ?すっごくかっこよくない?」
「え、ええ?」
促されるようにダニエリンはヴィオの顔を見た。
黒髪に淡い白銀色の瞳。ややつり上がり気味の大きな目と、整ったつり気味の眉。鼻も口もとても整っていて、卵型の綺麗な頭部は小さく、背はそんなに高い方ではなかったがすらりとして見えた。
「え、ええ…かっこいいと思うけど…」
「だよねっだよねっ!!いやーいい拾いものをしたよ僕ったら」
「…何下世話な好色おやじみたいな物言いしてるんですか全く」
ヴィオは溜め息をついた。
「ヴィオはね、ただの人間なの。なのにこんなに美しいんだよ。ずるいと思わない?」
「えっ」
ダ ニエリンはますます驚いた。この白廊期に入り、世界の三分の二は占めていると言われるほど生殖能力の高い人間と言う種族を、ダニエリンもまた少なからず見 てきてはいる。彼らはドラゴンや巨人といった魔族や、妖精や小人(ドワーフ)などの精霊とは違い、自然を生き自然を統べる能力は持たない代わりに、彼らと は違って子孫を増やす能力が著しく高く、また、自然に縛られずに生きられるために、独自の文化を築き生き抜くことができる。
魔族や精霊は、自然の力を支配できる代わりに自然と密接につながっているため、たとえば人間が言うところの『天災』が起こると、人間よりもはるかにその危険の餌食になる。
第三世代に当たるこの白廊期でここまで魔族や精霊の数が減ったのは、それも原因となっていた。
とはいえ、人間の生殖能力の高さは本当にすごい。その分人間は老化も早く、すぐに死んでしまうし、あまり美しい容姿をしているとは言えない。
けれどこのヴィオという少年は、魔族や精霊に匹敵するような美しさを有していた。
「その…精霊か何かの血が入っているとかじゃなく?」
ダニエリンがおずおずと尋ねると、ヴィオは首を振った。
「残念ながら…な。というか、そもそも僕はたしかに同種の中ではいい方かもしれないが、そこにいるエコーやフィガロンには遠く及ばない。まったく…エコーの物好きも大概にしてほしいな」
「ただ綺麗な奴なんてわんさかいるんだよ、ヴィオ。だけどね、君みたいにかっこいい人はそうそういないと僕は思ったの」
エコーはにっこりと笑った。
「戦闘時のヴィオのかっこよさなんて半端ないよ。僕はそれに惚れこんで彼を拾っちゃったんだから」
「ひ、拾った?」
「その人、迷い人を拾うのが趣味なんですの。しかもかなりどうでもいい理由で、ね」
「ど、どうでもいい理由…」
「そ。たとえば―あなただったら『髪の毛が蜂蜜みたいで美味しそうだから』、彼だと『むちゃくちゃかっこよかったから』、わたしは『そういえばまだ魔女を拾ってなかったから』、とか」
「ま、魔女」
「そ。ばかばかしい理由ですわよねえ、まったく」
「ばからしくはないでしょ。そもそも君を拾った理由はたしかに『魔女はまだ仲間にいなかった』ってのもあるけど、どっちかというと『泣き顔が綺麗だった』だからね」
エリカは顔をそむけた。頬が真っ赤になっている。
「魔女って…絶滅したんじゃなかったの?」
ダニエリンはエコーは無視することにして、聞いてみた。
魔女、という種族は少し特殊だ。髪の色や瞳の色、あるいは姿形まで自由自在に操ることができるし、無機物の姿形を変えることもできる。けれどその能力はほとんどが女の子孫にしか遺伝しない。稀に男にも遺伝することはあるが、その男児には生殖能力がない。
また、力としては他の魔族よりも破壊的なものではないため、人間と共に暮らしていた。一説には、魔力を遺伝できなかった者たちが人間として進化したとも言 われてもいる。けれど人間たちは、魔女たちの特異な能力を恐れて彼女たちを火あぶりの刑にし、その数は激減した。紅殿期のことである。
紅殿期の終わり、世界の中心に在った大火山ギュロストが噴火をおこし、世界は火に包まれた。その時、ほとんどの種族が壊滅的なダメージを受け、数の少なかった魔女などは絶滅してしまったと伝えられていた。
エリカはちょっとだけ舌を出した。
「まあ…そうね、今も百人いればいい方なんじゃないかしらね。今でも魔女裁判は続いているみたいだし」
「こんな凶暴な魔女、拾ったのは失敗だと思うけどねーオレは」
だるそうな声が聞こえてきた。ふと見やると、月明かりに照らされて一人の長身の少年が姿を現した。赤みを帯びた銀髪が、月光に映えている。
ものすごく美少年だった。いや、美青年と言った方がいいのだろうか。
とても大人っぽい雰囲気を持っている。色っぽいとでも言うのだろうか。
少年はダニエリンを見てにっと屈託なく笑った。口元から八重歯がのぞく。
「あれ、お嬢さん。気がついたんだね?よかったよかった」
その淡い橙色の瞳に見つめられると、なぜかくらっとした。
銀髪の少年はそっとダニエリンの手をとるとその甲に口付けした。ぼっと音が鳴るほど急激にダニエリンの顔は熱を帯びた。
「ま、ままま待って待って!?近い!近い近い顔が近いっ!?」
「おっと、失礼。無粋なことをしてごめんね?」
少年は首をかしげてにっこり笑った。
色っぽい。ものすごく色っぽい。
エリカが溜め息をついた。
「なあにーぃ?今日は満月ですのー?」
「エリカったら、そんなしかめてばっかりいたら眉間に縦じわが刻まれちゃうってば」
少年はきょとんとした顔で言った。
うっ、という声を漏らしてエリカはまた顔をそむけた。顔が赤い。少年はずるい笑みを浮かべてエリカの腰を引きよせた。
「あれー?どうしたのかなあ。いつもはバカ猫バカ猫言ってくれてるくせに…成体のオレを見るとそうやって恥じらって来るよねーあんた。そそるよねーどうしようか…たべちゃおっか…」
エリカの顔がゆでダコのようになる。
「離せっ…離しなさい…」
「あれー?その割に体に力入ってないよね?腰が抜けちゃった?ほんとは好きなんだろ?」
ダニエリンは顔をそむけることもできず目が離せないままどんどん頬に熱が上がってくるのがわかった。するとダニエリンの横でふっと鋭い風が起こる。
「ぐえっ」
苦しげな声が銀髪の少年から漏れた。
エコーがものすごく黒い笑顔で少年の首を絞めている。
「ははははは、ごめんね?そーゆー女ったらしな人種を見るとどーーーーーしても鞭でビシバシ叩いて腰が立たないようにしてやりたくなるんだよねー僕」
少年の額から脂汗がにじみ、眼は白目になっている。
「え、エコー!!やめてあげて…!!」
ダニエリンが悲鳴をあげると同時に、少年の腕からエリカも抜け出した。その途端。
パシーーーーーーーーーーン!!!!
どこから取り出したかわからない鞭がエコーの手の中でしなる。
「いたいた痛いっ!!痛いっっったらっ!!」
少年は悲鳴をあげた。
パシーン。パシーン。バシパシーン。
ダニエリンはいてもたってもいられず気付いた時には少年とエコーの間に滑り込んで少年を抱きしめかばっていた。
エコーの鞭がぴたり、と空中で止まる。
「ふ、ふえ…」
少年が泣きべそをかきながら息を吐いた。エコーが黒い笑顔でダニエリンに迫る。
「ふううううううううん…君はそいつをかばうんだあ?そいつに惚れちゃったのー?」
「へ?ええっ!?ち、違うわ、ただわたしは―」
「なああああああああにいいいいいい???」
ひいっ。
ダニエリンは悲鳴をあげそうになったが、頑張って立ち向かう。
「だ、だってこんな綺麗な人なのに、は、肌に傷つけちゃだめよっ」
しーん。
チリチリン、と虫の鳴く声がする。
しばらく一同は呆けたようにその場に立ち尽くしていた。
「あはっ」
静寂を破るのはエコーの笑い声。腹を抱えてひいひいと笑った。
「な、なるほろ…はは、はははっ。うんうん、わかったわかった…あははっ」
銀髪の少年は感激したようにダニエリンをぎゅうっと抱きしめた。
「大好きっ。やべえ惚れたっ!!嫁に来てくれ!!」
「え、えええええ!?」
「それとこれとは話が別だろーバカ猫っ」
べちん。
エコーがけろっとして半眼で少年の頭をはたいた。
銀髪の少年はむすっとする。
「猫じゃねえ!!オレは虎だって一体何回言えば…!!」
「あー煩い煩い」
「あ、あのう…この人、もしかして…」
ダニエリンはおずおずと口を開いた。
もう一人いるはずの仲間の姿が見えない。そして明らかにこの少年の髪の色や瞳の色は、あのにゃんこ言葉をしゃべっていた少年のものなのだ。
「…あの小さい子?」
「そーなんだよよく気付いてくれましたっ!!」
銀髪の少年は眼をうるませてダニエリンに迫る。
「だからいちいち顔が近いっつってんだよっ」
苛立ったようにエコーがその髪の毛を引っ張ってダニエリンから少年の顔を引き離す。
涙をにじませながら、くしゃっと少年は笑った。
「オレ、フィガロン=ドゥケ!!虎族の王子なの!!ま、王子っつっても五番目なんで王位には関係ないんだけどね」
フィガロンは頬を掻いた。
「ああ…」
ダニエリンは空を見上げた。今日は満月だ。
「満月だから生体化したのね?」
「いや…まあ、そうなんだけど…」
フィガロンは歯切れが悪い。
「そもそもこいつは元から成人している。だから本来は満月の夜は力が著しく増幅する、ということなんだけどな」
ヴィオが淡々と言った。
「見てのとーり、成体でいると異常なまでに色気が出ていて周りに害しか及ぼさないからね、普段は僕の魔力で封じてちび化させてるの。ま、満月になるとそれも効かなくなるんだけど」
「ほんとひでえよ…そんなのどの虎族にもある話じゃねえかよ。なのになんでオレだけ…」
「だってあんた、虎族にしては美形すぎるじゃないの」
落ち着いたらしいエリカが言った。
「そもそも虎族の男はね、顔が不細工だから生殖のために過剰なフェロモンを出すもんなのよ?なのに素で女にもてる容姿をしていてさらにそんなフェロモン出されたら女の方がたまったもんじゃないわよ」
「別にいいじゃん…むしろオレの子供は美形になりそうでいいと思うけど?」
フィガロンは膨れたように言った。
「ふっ…親が美形だからと言ってそうなるとは限らないのが世の不条理…」
「うわエコー!!やめてくれそんな憐みの眼でそんなこと言うの!!?」
「まあたしかに…エコーの兄弟見てればわかるだろう」
ヴィオが言った。
「どういうこと?」
ダニエリンが首をかしげると、エコーが話を遮った。
「それよりさ、この子にちょっとは何か食べさせてあげようとは思わないわけ?目ぇ覚めて一体どれだけ立ってると思ってんの」
まるで示し合わせたかのようにダニエリンのお腹がぐう、となった。
「うう…」
ダニエリンは真っ赤になってうつむく。
「今日はねーえ?なんか色々採れたんだよ。だから気にせずたくさん食べなよ、ね」
エコーはにっこりと笑って、ポトフの串焼きらしきものをダニエリンに手渡した。
ダニエリンはそのかぐわしい香りに耐えきれなくなって恥も外聞もためらわずがっついてしまう。
恥ずかしかったが、同時に涙が出るほど美味しいと思った。幸せに思えた。
「そういえば―君、なんて名前?」
エコーもポトフをほおばりながら言う。
「は、はいへひ…」
「呑みこんでから言え、せめて」
ヴィオが呆れたように言う。
ダニエリンは、肉をごくん、の呑みこんだ。
「ダニエリン。ダニエリン=レスコよ」
「へえ、綺麗な名前」
エコーはにっこりと嬉しそうに笑った。
「僕はねえ、エコース=リュア。ま、普段はエコーって呼ばれてるけどね。で、この人がヴィオ=マリオスでしょ、あの子がエリカ=ロンドン、あれが…ってフィグはさっき名乗ったか」
「だーかーらー、フィグって呼ぶなって何度も言ってんだろうが。その愛称嫌いなんだよ!」
「うん知ってるけど?」
「っ…このやろう…!!」
フィガロンはエコーをねめつけると、すがるような眼差しでダニエリンを見つめた。
「お願いだからフィグっては呼ばないでくれない?」
「う、うん…その、なんて呼べばいいの?フィガロ、とか?」
フィガロンは顔を輝かせた。
「ああ、それいいね!いいよ!じゃあお嬢さんはオレのことそう呼んでよ!!今のが一番気にいった!!」
「まあ…わたしは彼のことロンって呼んでたんですけどね。ヴィオはそのままでしたけど」
「あーめんどくさい。仲間内でなんで一匹の名前をいろんな呼び方で呼んでやらなきゃいけないのさ、そこまでの重要人物じゃなし」
「うるせーよ!!オレがいつお前に迷惑かけたよ!?なんだよいつもケンカばっか売りやがって!!」
「今まさに迷惑かけてると思うけど」
「何をぅ!?」
「…いい加減にしないと殺すぞ」
どす黒い声でヴィオが言い放ち、腰の鞘から刀を抜いた。フィガロンはしゅん、とうなだれる。
「なんでいつもオレばっか怒られんのさ…」
なんだか捨てられた仔猫みたいだ、とダニエリンは思った。なんとなくその頭をなでてやる。
フィガロンは眼を丸くしたがすぐに涙をにじませた。
「ううううう…優しいよ…お嬢さん…よかった、この子を拾ってくれて、エコーが」
「別にお前のために拾ったんじゃなく僕のために拾ったんだけどね」
エコーはそっけなく言った。
「ダニエリン…か…長いしやっぱ愛称は必要だよね。どう思う?エリー」
エリカはピットをつまみながらふむ、と思案した。
「そうねえ…ダニーとかエリン…いえそれじゃわたしと被りますわね…あ、アニーとか可愛らしいと思いますけれど!」
「うん、じゃあそれで。よろしくアニー」
「え、えええ!?」
「すまないがうちの主は非常な面倒臭がりなんだ…名前の簡略化に協力してほしい」
「うわ、酷い言いようだね」
「事実でしょう」
「まあそうだけど」
「酷いっ。なんでヴィオにはいつも甘いのさ!!オレがおんなじこと言ったら絶対酷い目に遭わせるくせにっ」
「煩いバカ猫黙れバカ猫食い物減らされたくなかったら三べん回ってワンと鳴いてみろバカ猫」
「ね、猫って言いながらなんで犬の鳴きまねさせようとするんだよっ!?」
「ええとその…」
ダニエリンは苦笑した。
「ものすっごくアホなやり取りするのね、あなたたち」
しん、と辺りが静かになる。
何か変なことを言っただろうかとダニエリンは思った。
ダニエリンは、かなりの毒舌でかつ物事をひねくれて見る節があるのだが、本人にはまったく自覚がない。
やがてエコーがまた爆笑し始めた。
「あっははははははっ。うわあ…こんな面白い子初めて会ったかもっ」
目じりに涙まで浮かべている。
「…わたし別に面白いこと言った覚えないけど…」
「まあ、これからエコーと十分渡り合えそうな程度には面白かったですわよ」
エリカもくすくすと笑っている。ただ、フィガロンだけは青ざめていた。
ヴィオが生ぬるい微笑みを向けてくる。
「まあ…せいぜいエコーの堪忍袋の緒が切れない程度には健闘してくれ…それなりに、面白いから」
「ど、どういう意味?」
「あ、なんかその言い種ひどくなーい、ヴィオくん?」
「そうですか?」
「気のせいですわよ」
「へーえ?二人して僕の敵にまわるんだあ?」
エコーがにやりと笑う。対する二人は余裕の笑みを崩さない。
―仲がいいんだか悪いんだかさっぱり分からないな、この集団。
ダニエリンは心の中で呟いた。
そしてふと、いつの間にか温かい気持ちになっていることに気付く。
この四人の傍にいると、暗い過去を忘れていられる気がした。
そのことに罪悪感を感じながらも、このまままどろんでいたい、とダニエリンは思わずにはいられなかった。
三、煩いんだけど。
第一部
第一章
一、蜂蜜みたい
そこは深い深い森の中。
一人の少女が、ふらふらとしながら彷徨っている。
少女は蜂蜜のような美しい深みのある金髪に、コスモスのような青みを帯びた淡紅色の瞳をしていた。
もう長いことまともなものを食べていない。おかげで視界はぼんやりとして、頭はずきずきと痛んでいた。腹は空いていたが、ここまで来ると疲労ばかりで何か食べ物を探そうという気力さえ湧いてくれない。
少女はとりあえず一本の木の根元に腰をおろして、まどろみ始めた。
糖分の欠乏している体は、すぐに眠りについてしまう。眠っている間が一番楽だった。目が覚めると酷く空腹を感じて、苦しくなる。立つと目眩もするし、本当に、そろそろこのままあの世へいきたいと、ぼんやりそんなことまで考えてしまっていた。
―苦しい。
ひくひく、と喉が震えた。少女は自分が幼子のようにみっともなく泣いていることに気付く。
自分でも、情けないと思った。一体自分はどれほどの命を勝手に奪っただろう。それでも死ぬことに自分で涙を流している。なんて自分勝手な生き物だろう。
少女は、異種族間のハーフだった。ハーフは何も珍しいことではない。けれどその中でも彼女は特殊だった。
普通異種族間の契りというのは同じくらいの力あるいは体格のある者同士で結ばれる。そうでなければならない。もしも母親と父親との間に能力や体格的な差異 がありすぎると、生まれてくる子供はその差分に苦しめられることになる。己の体の中で相反する力が拮抗し、その反動で内に溜まりに溜まった破壊的な力を衝 動的に外へ排出しなければ自己を保てなくなるのだ。
つまり、発作的に周囲を巻き込む力の大暴走を起こしてしまうことになる。
少女こそ、その類だった。
小人の類に入り、虫ほどの力しか持たない妖精の母親が、魔族と呼ばれる超能力を有する種族の中でも高位に位置する竜族(ドラゴン)の青年との間に設けた子供が彼女だった。
あまりにも開きすぎている力の差は、そのまま彼女の内で膨大なエネルギーとして溜まり、彼女を苦しめる。そして、彼女の意思とは関係なく、本能的に、周期的にそのエネルギーは爆発し、周囲を焼き尽くしてしまうのだ。
そのせいで、彼女は今まで罪もない人々をどれほど殺してしまったか、もう分からない。
けれどどうすることもできない。だから彼女はただ逃げていた。できるだけ遠くへ、誰も周りにいない世界へ、辿り着くため。
そのうち、この、終点も見えない深い森の中に迷い込んでしまったというわけだった。いつしか食べられるものすら見当たらなくなり、飢え死に寸前の状況に陥っている。
けれど少女は、それでも悪くない、とも思っていた。
ここで死ぬのも当然かもしれない。それだけの罪を自分は重ねてきたのだから。
それなのに、いざ死を目の前にすると、死にたくないという思いがわき上がってくることが情けなくて仕方がなかった。
一体どうしたらよかったというのだろう。
少女は、こらえきれず嗚咽を漏らした。こんな力が欲しかったわけじゃない。こんな思いをするために生まれたのなら、生まれてきたくなどなかった。
どうして母親は自分を産んだのだろう。何故ドラゴンと契りを結んだのだろう。
母親にぶつけたかった言葉は、ひとつもぶつけることができなかった。彼女は、胎児の持つ絶大な力のせいで、彼女を産む直前に息絶えたのだから。少女は死ん でしまった母親の腹から急いで取り出された。助かったのは彼女だけだ。少女は間もなく、自身の力で母親の生まれ育った妖精の村をも破壊してしまった。
「おかしいなあ。いい匂いがしたと思ったんだけど」
「だから、気のせいではありませんこと?こんなところに食べ物があるわけでもなし」
「あるいは、餌を呼び寄せる毒花の出す香の類かと思います」
「うわ…やめてよ、わたしは花の餌食になんかなりたくありませんわよ」
「俺だって御免こうむりたいです」
「煩いなあ。ちょっと黙っててよ。分からなくなるじゃない」
「…言っときますけれど、嗅覚と聴覚はまったくもって連動しませんわよ」
「いたいた痛いっ!!引っ張らないでよっ」
「え?って、引っ張ってなんかいません!!勝手にあなたが髪をわたしの服に絡ませてるだけでしょう!!」
「オレのせいじゃにゃいもん!!い痛っ」
少女ははた、と顔をあげた。
場にそぐわないような能天気な会話がどこからか聞こえてくる。
いつの間にか涙は止まってしまっていた。力が抜けて、少女はその場で呆けてしまう。がさがさ、と頭上で音がして、何かがぬっと少女の眼の前に影を作った。
「あれ」
影が呑気な声を出した。逆光でよく見えないが、少年の逆さの顔のようだ。そもそも少女は視界もかすんでいるから、よけいによくわからない。
「ねえ、こんなところに女の子がいるよっと」
少年はそのままくるっと体を空中で回転させて地上に降りてきた。続けて黒い影が三つ、ざざっと音を立てて上から降ってきた。
「どれどれ…ってこの子!!死にかけてるじゃありませんの!?」
少女らしき可愛らしい声が小さな悲鳴をあげた。
「見たところ、栄養失調ってところですね。この森に迷い込んだものの一般的な末路の図です」
淡々とした、抑揚のない少年らしき声が続いた。
「そ、そんなこと見れば分かりますわ!」
「というか助けてあげにゃいのー?」
「煩いわよバカ猫っ。何まともなこと言ってやった顔してますのっ」
「にゃっ!?にゃ、にゃにか文句でもあるのか!?」
「あー煩い煩い。喧嘩ならあっちでやってくれる?僕たちに被害の出ないところで」
最初に降りてきた少年が手をひらひらと振って言った。
薄い青緑色の、森のような色の髪をしているのだけはわかる。そして肌が目が覚めるほど白いことも。けれどそれ以上はかすんだ目ではよく見ることができない。
少年は少女の眼の前で手をひらひらとかざした。
「見えるー?」
少女は首を横に振った。
「ふーん…焦点あってないなあとは思ってはいたんだけど、ね。ねえヴィオ、この子目が見えない子なのかな」
「その可能性も確かにありますが、栄養失調が過ぎると視力に異常をきたすことがあります。その場合は栄養さえ取ればしばらくすると治るはずですが」
「なーる。何かとりあえず食べさせてあげる?あと何が残ってたっけ」
「ファビの缶詰があと三つ、フォトフの燻製が七枚、あと昨日採ったクレオの焼いたのがまだ五切れあったかと」
「…そろそろわたしたちの食糧源も危ないんじゃありません?」
「まあ、それもそうだけど。でもほら、見てよ、この子の髪。蜂蜜みたい。美味しそう。すごく美味しそう」
「…あなたが言うと洒落になりませんわ」
「にゃ…」
「ははははは。どういう意味かな?」
「まあ、蜂蜜みたいな色、というのは俺も同意です。美味しそうかどうかまではよくわかりませんけど」
「だよね。それにこの子、なんか甘いいい匂いがする」
少年がくんくん、と匂いを嗅いでいるのが分かった。少女は途端に恥ずかしくなってきた。
そもそもここ何日もこの森で彷徨っていたのだから、風呂にすら入れていない。少女は首をただ振った。
「…女の子の匂いを嗅ぐなんて変態なのにゃ…」
「煩い猫。何まともなこと言ってんだ猫のくせに」
「オ、オレ虎だもん…猫じゃにゃいもん…」
猫と呼ばれた幼い少年がべそをかいた。
「ヴィオ、クレオ寄こして」
ヴィオと呼ばれた黒髪の少年が背中に背負っていた荷物から何かを取り出す。焼いた魚のいい香りが少女の鼻をついた。動くのを忘れていた腹がまた活動を始めたのがわかった。少女はなんだか悲しくなって首を横に振った。
「い、いらない…わたしには、かまわないで、お願い」
「なぜ」
少女は言葉に詰まった。またじわりと涙が滲んできた。
「い、いいの。このままでいいの。このまま死なせてください。わたしは、死ななきゃだめなの」
「…随分悲しいことを言いますのね、この子」
淡紫色の髪をした少女が低い声で言った。
しばらく流れた沈黙を、最初の少年のくすくす笑いが破った。
少女は眼を見開いた。何故少年が楽しげに笑うのか理解ができなかった。
「へええ?死にたい、と。ふーん」
少年はなおもくすくす笑っている。
「あんた面白いね!」
少女は訳が分からなくて目を泳がせた。少年がにんまりと笑ったのがわかった。
「まあ、ほっとけば君は死ぬだろうね。ということで、ここからは僕たちが君の身柄を預からせてもらうことにします。いいよね?」
少年は振り返った。小さなため息が漏れた。
「まあ…やらかすだろうなとは思ってました」
「そうね…この人拾いものが趣味だし」
「い、いや…構わないで!わたしにかまわないで!」
少女は叫んだがかすれた声しか出なかった。
先の少年はきょとんとした顔で言った。
「え?だめだよ?僕君の髪の毛気に入っちゃったんだもの。蜂蜜みたいで美味しそう。このままみすみす逃しちゃうなんて、なんてもったいない」
少女は気が遠くなる想いがした。随分と横暴な少年に見つかってしまったらしい。
「で、ヴィオ、この子おぶってあげて?」
少年は首をちょこん、とかしげて見せた。黒髪の少年は溜め息をつきながら少女の傍に寄ってきた。
「…ご自分でおぶってあげる、という選択肢はないのかしら」
「だってーエリカ嬢。僕こんないたいけな子供だよ?つぶれちゃうよー」
「…その気になれば大人になれるでしょうあなたは」
ヴィオ、と呼ばれていた少年は少女を抱きかかえてたちあがった。
「あれーヴィオ!なにそれお姫様だっこ」
「…ですから、彼女は衰弱しているので変に負担をかけるよりもそのままの体勢のまま連れて行った方がいいかと判断しただけで」
ヴィオという少年は溜め息をつきながら言った。
その手から伝わる温もりは温かく優しくて、少女は意に反してまどろみ始めていた。
「ふふふ。嬉しいにゃー。可愛い女の子がまた仲間に増えるのにゃ」
「…こ…いつ、ガキになってもやっぱり女ったらしなのね…っ」
エリカ、と呼ばれた少女がうんざりしたように言った。
薄い青緑の髪の少年ももっとうんざりしたような声で言った。
「…成体になるとこんなもんじゃないしね…」
「エコー。お願いですから冥土に行くような表情にならないでください」
ヴィオが溜め息をつきながら言った。
「そもそもそんな彼を拾ったのもあなたでしょうが」
「…だってさ…フィグ見てたら…あれだよそう、『自分の父親を檻に入れてビシバシ躾けてやりたい気分になった』ってやつ」
エコーと呼ばれた少年は妙に黒い声で言った。
「フィグって呼ぶにゃ!!」
「煩い猫」
「ロン、あとでわたしの分のクレオ食べさせてあげますから機嫌直して」
エリカがため息交じりに言うと、銀髪の幼い少年は嬉しそうな声で喜んだ。
「わーいっ」
「眠ってていいですよ?」
ふと、ヴィオが少女がうとうとしているのに気付いて声をかけてきた。
「糖分が足りていないと眠くなるものですから。安心してください。落としはしませんから」
とてもぶっきらぼうだったが優しい声だった。
少女は抗うこともできずに、そのまま深い眠りに落ちていった。
二、面白い
ダニエリンが目を覚ますと、体中を幸せで満たしてくれるような、美味しそうな匂いが彼女を包んでくれていた。なんだかダニエリンは泣きたくなってしまった。
―食べたい。
そういう希望が出てきたことへの喜びと、悲しさと、恥ずかしさが彼女を苦しめた。
また、無意識にしゃくりあげていた。そんな彼女の横に、誰かが勢いよくしゃがみ込んだ。
はっと顔をあげると、淡い青緑色の柔らかな猫っ毛の少年が、にこっと笑っていた。
「あ、焦点あってるね。僕の顔見える?」
ダニエリンは自分でも驚いていた。いつの間にか、それでも普段よりはまだかすんでいるとはいえ、少年の顔が分かるほどまで視力が回復している。
「君がもう意識不明みたいになってたからね。ヴィオがずっと解放してくれてたんだよ。流動食作ってね、ずっと君の口に流し込んであげてたの。それはもう…甲斐甲斐しく口移しでっ」
「えっ…」
ダニエリンは絶句する。
「嘘八百並べないでください。流動食を作ったのも世話をしたのも確かに俺ですが口移しまではしていません」
ヴィオの少年らしいかすれ声が不機嫌そうに響いた。ヴィオはふっとダニエリンに笑いかけた。
「顔色もよくなったな。よかった」
「あれあれーなんかいい雰囲気だねっ。おにーさんはさっさと退散するね―」
「その花畑な思考を直していただくまではここにいていただきましょうかね?」
ヴィオが怒りにまみれた低い声で言って少年の襟首をつかんだ。
「まったく…ほんとにエコーはヴィオをからかうのが好きなんだから…」
エリカが苦笑する。そしてダニエリンの両頬をぱしん、と手で挟み打ちした。
「い痛っ!?」
「いいですこと?もう二度と、あんな哀しいことは言わないでください。分かりましたか?」
このまま死にたい、と言ったことだろうか、とダニエリンは思った。ダニエリンはエリカの金色の瞳の奥に真剣なものを感じ、半ば無意識にうなずいた。エリカは柔らかく微笑むと、エリカの頭を撫でくり回した。
最初はなんとなく嬉しい気もしたが、次第にエリカの瞳に宿ってきた何かを見て、ダニエリンは唖然とした。エリカは眼をハートにしてまくしたてた。
「で、ですわ…この子可愛いですわっ!!どうしましょうどうしましょう!!やっぱりここはフリルのいーっぱいついたドレスとか似合うと思いますの!!あ、でもミニも捨てがたいですわね!!どうしましょうかしらどうしましょうっ」
急に顔を真っ赤にして一人で悶え始めたエリカにダニエリンは茫然とした。
救いを求めるようにヴィオを見たが彼は眉間に指をあてて顔をそむけている。
「だよね?この子結構可愛いと思ったんだよね僕」
「はあ!?」
ダニエリンは思わず声をあげた。
エコーと呼ばれていた少年はじいっとダニエリンの顔を覗き込んだ。その男の子にしてはあまりにも整い綺麗すぎる顔に、ダニエリンは顔が紅潮するのがわかった。
薄いパールブルーの大きな瞳が、ものすごく神秘的で綺麗だ。
「うん、こんな綺麗な金髪初めて見たし、そもそもこんなコスモスみたいな目も初めてだ。すっごく綺麗。君もしかして妖精の血引いてるでしょ」
ダニエリンはびくり、と肩をはねさせた。なるべく答えたくない。けれどエコーの眼差しに勝てそうにもない。ダニエリンはあっけなく白旗をあげた。
「う、うん…」
「やっぱりね!!こんな美しい種族なんて、妖精と巨人族くらいしかいないよね!!ま、巨人族にはもう女の子はいないけど」
気のせいか、最後の言葉には何か刺が含まれていたような気がした。
「とはいえ、ね、君はヴィオのことどう思う?すっごく顔綺麗でしょ?すっごくかっこよくない?」
「え、ええ?」
促されるようにダニエリンはヴィオの顔を見た。
黒髪に淡い白銀色の瞳。ややつり上がり気味の大きな目と、整ったつり気味の眉。鼻も口もとても整っていて、卵型の綺麗な頭部は小さく、背はそんなに高い方ではなかったがすらりとして見えた。
「え、ええ…かっこいいと思うけど…」
「だよねっだよねっ!!いやーいい拾いものをしたよ僕ったら」
「…何下世話な好色おやじみたいな物言いしてるんですか全く」
ヴィオは溜め息をついた。
「ヴィオはね、ただの人間なの。なのにこんなに美しいんだよ。ずるいと思わない?」
「えっ」
ダ ニエリンはますます驚いた。この白廊期に入り、世界の三分の二は占めていると言われるほど生殖能力の高い人間と言う種族を、ダニエリンもまた少なからず見 てきてはいる。彼らはドラゴンや巨人といった魔族や、妖精や小人(ドワーフ)などの精霊とは違い、自然を生き自然を統べる能力は持たない代わりに、彼らと は違って子孫を増やす能力が著しく高く、また、自然に縛られずに生きられるために、独自の文化を築き生き抜くことができる。
魔族や精霊は、自然の力を支配できる代わりに自然と密接につながっているため、たとえば人間が言うところの『天災』が起こると、人間よりもはるかにその危険の餌食になる。
第三世代に当たるこの白廊期でここまで魔族や精霊の数が減ったのは、それも原因となっていた。
とはいえ、人間の生殖能力の高さは本当にすごい。その分人間は老化も早く、すぐに死んでしまうし、あまり美しい容姿をしているとは言えない。
けれどこのヴィオという少年は、魔族や精霊に匹敵するような美しさを有していた。
「その…精霊か何かの血が入っているとかじゃなく?」
ダニエリンがおずおずと尋ねると、ヴィオは首を振った。
「残念ながら…な。というか、そもそも僕はたしかに同種の中ではいい方かもしれないが、そこにいるエコーやフィガロンには遠く及ばない。まったく…エコーの物好きも大概にしてほしいな」
「ただ綺麗な奴なんてわんさかいるんだよ、ヴィオ。だけどね、君みたいにかっこいい人はそうそういないと僕は思ったの」
エコーはにっこりと笑った。
「戦闘時のヴィオのかっこよさなんて半端ないよ。僕はそれに惚れこんで彼を拾っちゃったんだから」
「ひ、拾った?」
「その人、迷い人を拾うのが趣味なんですの。しかもかなりどうでもいい理由で、ね」
「ど、どうでもいい理由…」
「そ。たとえば―あなただったら『髪の毛が蜂蜜みたいで美味しそうだから』、彼だと『むちゃくちゃかっこよかったから』、わたしは『そういえばまだ魔女を拾ってなかったから』、とか」
「ま、魔女」
「そ。ばかばかしい理由ですわよねえ、まったく」
「ばからしくはないでしょ。そもそも君を拾った理由はたしかに『魔女はまだ仲間にいなかった』ってのもあるけど、どっちかというと『泣き顔が綺麗だった』だからね」
エリカは顔をそむけた。頬が真っ赤になっている。
「魔女って…絶滅したんじゃなかったの?」
ダニエリンはエコーは無視することにして、聞いてみた。
魔女、という種族は少し特殊だ。髪の色や瞳の色、あるいは姿形まで自由自在に操ることができるし、無機物の姿形を変えることもできる。けれどその能力はほとんどが女の子孫にしか遺伝しない。稀に男にも遺伝することはあるが、その男児には生殖能力がない。
また、力としては他の魔族よりも破壊的なものではないため、人間と共に暮らしていた。一説には、魔力を遺伝できなかった者たちが人間として進化したとも言 われてもいる。けれど人間たちは、魔女たちの特異な能力を恐れて彼女たちを火あぶりの刑にし、その数は激減した。紅殿期のことである。
紅殿期の終わり、世界の中心に在った大火山ギュロストが噴火をおこし、世界は火に包まれた。その時、ほとんどの種族が壊滅的なダメージを受け、数の少なかった魔女などは絶滅してしまったと伝えられていた。
エリカはちょっとだけ舌を出した。
「まあ…そうね、今も百人いればいい方なんじゃないかしらね。今でも魔女裁判は続いているみたいだし」
「こんな凶暴な魔女、拾ったのは失敗だと思うけどねーオレは」
だるそうな声が聞こえてきた。ふと見やると、月明かりに照らされて一人の長身の少年が姿を現した。赤みを帯びた銀髪が、月光に映えている。
ものすごく美少年だった。いや、美青年と言った方がいいのだろうか。
とても大人っぽい雰囲気を持っている。色っぽいとでも言うのだろうか。
少年はダニエリンを見てにっと屈託なく笑った。口元から八重歯がのぞく。
「あれ、お嬢さん。気がついたんだね?よかったよかった」
その淡い橙色の瞳に見つめられると、なぜかくらっとした。
銀髪の少年はそっとダニエリンの手をとるとその甲に口付けした。ぼっと音が鳴るほど急激にダニエリンの顔は熱を帯びた。
「ま、ままま待って待って!?近い!近い近い顔が近いっ!?」
「おっと、失礼。無粋なことをしてごめんね?」
少年は首をかしげてにっこり笑った。
色っぽい。ものすごく色っぽい。
エリカが溜め息をついた。
「なあにーぃ?今日は満月ですのー?」
「エリカったら、そんなしかめてばっかりいたら眉間に縦じわが刻まれちゃうってば」
少年はきょとんとした顔で言った。
うっ、という声を漏らしてエリカはまた顔をそむけた。顔が赤い。少年はずるい笑みを浮かべてエリカの腰を引きよせた。
「あれー?どうしたのかなあ。いつもはバカ猫バカ猫言ってくれてるくせに…成体のオレを見るとそうやって恥じらって来るよねーあんた。そそるよねーどうしようか…たべちゃおっか…」
エリカの顔がゆでダコのようになる。
「離せっ…離しなさい…」
「あれー?その割に体に力入ってないよね?腰が抜けちゃった?ほんとは好きなんだろ?」
ダニエリンは顔をそむけることもできず目が離せないままどんどん頬に熱が上がってくるのがわかった。するとダニエリンの横でふっと鋭い風が起こる。
「ぐえっ」
苦しげな声が銀髪の少年から漏れた。
エコーがものすごく黒い笑顔で少年の首を絞めている。
「ははははは、ごめんね?そーゆー女ったらしな人種を見るとどーーーーーしても鞭でビシバシ叩いて腰が立たないようにしてやりたくなるんだよねー僕」
少年の額から脂汗がにじみ、眼は白目になっている。
「え、エコー!!やめてあげて…!!」
ダニエリンが悲鳴をあげると同時に、少年の腕からエリカも抜け出した。その途端。
パシーーーーーーーーーーン!!!!
どこから取り出したかわからない鞭がエコーの手の中でしなる。
「いたいた痛いっ!!痛いっっったらっ!!」
少年は悲鳴をあげた。
パシーン。パシーン。バシパシーン。
ダニエリンはいてもたってもいられず気付いた時には少年とエコーの間に滑り込んで少年を抱きしめかばっていた。
エコーの鞭がぴたり、と空中で止まる。
「ふ、ふえ…」
少年が泣きべそをかきながら息を吐いた。エコーが黒い笑顔でダニエリンに迫る。
「ふううううううううん…君はそいつをかばうんだあ?そいつに惚れちゃったのー?」
「へ?ええっ!?ち、違うわ、ただわたしは―」
「なああああああああにいいいいいい???」
ひいっ。
ダニエリンは悲鳴をあげそうになったが、頑張って立ち向かう。
「だ、だってこんな綺麗な人なのに、は、肌に傷つけちゃだめよっ」
しーん。
チリチリン、と虫の鳴く声がする。
しばらく一同は呆けたようにその場に立ち尽くしていた。
「あはっ」
静寂を破るのはエコーの笑い声。腹を抱えてひいひいと笑った。
「な、なるほろ…はは、はははっ。うんうん、わかったわかった…あははっ」
銀髪の少年は感激したようにダニエリンをぎゅうっと抱きしめた。
「大好きっ。やべえ惚れたっ!!嫁に来てくれ!!」
「え、えええええ!?」
「それとこれとは話が別だろーバカ猫っ」
べちん。
エコーがけろっとして半眼で少年の頭をはたいた。
銀髪の少年はむすっとする。
「猫じゃねえ!!オレは虎だって一体何回言えば…!!」
「あー煩い煩い」
「あ、あのう…この人、もしかして…」
ダニエリンはおずおずと口を開いた。
もう一人いるはずの仲間の姿が見えない。そして明らかにこの少年の髪の色や瞳の色は、あのにゃんこ言葉をしゃべっていた少年のものなのだ。
「…あの小さい子?」
「そーなんだよよく気付いてくれましたっ!!」
銀髪の少年は眼をうるませてダニエリンに迫る。
「だからいちいち顔が近いっつってんだよっ」
苛立ったようにエコーがその髪の毛を引っ張ってダニエリンから少年の顔を引き離す。
涙をにじませながら、くしゃっと少年は笑った。
「オレ、フィガロン=ドゥケ!!虎族の王子なの!!ま、王子っつっても五番目なんで王位には関係ないんだけどね」
フィガロンは頬を掻いた。
「ああ…」
ダニエリンは空を見上げた。今日は満月だ。
「満月だから生体化したのね?」
「いや…まあ、そうなんだけど…」
フィガロンは歯切れが悪い。
「そもそもこいつは元から成人している。だから本来は満月の夜は力が著しく増幅する、ということなんだけどな」
ヴィオが淡々と言った。
「見てのとーり、成体でいると異常なまでに色気が出ていて周りに害しか及ぼさないからね、普段は僕の魔力で封じてちび化させてるの。ま、満月になるとそれも効かなくなるんだけど」
「ほんとひでえよ…そんなのどの虎族にもある話じゃねえかよ。なのになんでオレだけ…」
「だってあんた、虎族にしては美形すぎるじゃないの」
落ち着いたらしいエリカが言った。
「そもそも虎族の男はね、顔が不細工だから生殖のために過剰なフェロモンを出すもんなのよ?なのに素で女にもてる容姿をしていてさらにそんなフェロモン出されたら女の方がたまったもんじゃないわよ」
「別にいいじゃん…むしろオレの子供は美形になりそうでいいと思うけど?」
フィガロンは膨れたように言った。
「ふっ…親が美形だからと言ってそうなるとは限らないのが世の不条理…」
「うわエコー!!やめてくれそんな憐みの眼でそんなこと言うの!!?」
「まあたしかに…エコーの兄弟見てればわかるだろう」
ヴィオが言った。
「どういうこと?」
ダニエリンが首をかしげると、エコーが話を遮った。
「それよりさ、この子にちょっとは何か食べさせてあげようとは思わないわけ?目ぇ覚めて一体どれだけ立ってると思ってんの」
まるで示し合わせたかのようにダニエリンのお腹がぐう、となった。
「うう…」
ダニエリンは真っ赤になってうつむく。
「今日はねーえ?なんか色々採れたんだよ。だから気にせずたくさん食べなよ、ね」
エコーはにっこりと笑って、ポトフの串焼きらしきものをダニエリンに手渡した。
ダニエリンはそのかぐわしい香りに耐えきれなくなって恥も外聞もためらわずがっついてしまう。
恥ずかしかったが、同時に涙が出るほど美味しいと思った。幸せに思えた。
「そういえば―君、なんて名前?」
エコーもポトフをほおばりながら言う。
「は、はいへひ…」
「呑みこんでから言え、せめて」
ヴィオが呆れたように言う。
ダニエリンは、肉をごくん、の呑みこんだ。
「ダニエリン。ダニエリン=レスコよ」
「へえ、綺麗な名前」
エコーはにっこりと嬉しそうに笑った。
「僕はねえ、エコース=リュア。ま、普段はエコーって呼ばれてるけどね。で、この人がヴィオ=マリオスでしょ、あの子がエリカ=ロンドン、あれが…ってフィグはさっき名乗ったか」
「だーかーらー、フィグって呼ぶなって何度も言ってんだろうが。その愛称嫌いなんだよ!」
「うん知ってるけど?」
「っ…このやろう…!!」
フィガロンはエコーをねめつけると、すがるような眼差しでダニエリンを見つめた。
「お願いだからフィグっては呼ばないでくれない?」
「う、うん…その、なんて呼べばいいの?フィガロ、とか?」
フィガロンは顔を輝かせた。
「ああ、それいいね!いいよ!じゃあお嬢さんはオレのことそう呼んでよ!!今のが一番気にいった!!」
「まあ…わたしは彼のことロンって呼んでたんですけどね。ヴィオはそのままでしたけど」
「あーめんどくさい。仲間内でなんで一匹の名前をいろんな呼び方で呼んでやらなきゃいけないのさ、そこまでの重要人物じゃなし」
「うるせーよ!!オレがいつお前に迷惑かけたよ!?なんだよいつもケンカばっか売りやがって!!」
「今まさに迷惑かけてると思うけど」
「何をぅ!?」
「…いい加減にしないと殺すぞ」
どす黒い声でヴィオが言い放ち、腰の鞘から刀を抜いた。フィガロンはしゅん、とうなだれる。
「なんでいつもオレばっか怒られんのさ…」
なんだか捨てられた仔猫みたいだ、とダニエリンは思った。なんとなくその頭をなでてやる。
フィガロンは眼を丸くしたがすぐに涙をにじませた。
「ううううう…優しいよ…お嬢さん…よかった、この子を拾ってくれて、エコーが」
「別にお前のために拾ったんじゃなく僕のために拾ったんだけどね」
エコーはそっけなく言った。
「ダニエリン…か…長いしやっぱ愛称は必要だよね。どう思う?エリー」
エリカはピットをつまみながらふむ、と思案した。
「そうねえ…ダニーとかエリン…いえそれじゃわたしと被りますわね…あ、アニーとか可愛らしいと思いますけれど!」
「うん、じゃあそれで。よろしくアニー」
「え、えええ!?」
「すまないがうちの主は非常な面倒臭がりなんだ…名前の簡略化に協力してほしい」
「うわ、酷い言いようだね」
「事実でしょう」
「まあそうだけど」
「酷いっ。なんでヴィオにはいつも甘いのさ!!オレがおんなじこと言ったら絶対酷い目に遭わせるくせにっ」
「煩いバカ猫黙れバカ猫食い物減らされたくなかったら三べん回ってワンと鳴いてみろバカ猫」
「ね、猫って言いながらなんで犬の鳴きまねさせようとするんだよっ!?」
「ええとその…」
ダニエリンは苦笑した。
「ものすっごくアホなやり取りするのね、あなたたち」
しん、と辺りが静かになる。
何か変なことを言っただろうかとダニエリンは思った。
ダニエリンは、かなりの毒舌でかつ物事をひねくれて見る節があるのだが、本人にはまったく自覚がない。
やがてエコーがまた爆笑し始めた。
「あっははははははっ。うわあ…こんな面白い子初めて会ったかもっ」
目じりに涙まで浮かべている。
「…わたし別に面白いこと言った覚えないけど…」
「まあ、これからエコーと十分渡り合えそうな程度には面白かったですわよ」
エリカもくすくすと笑っている。ただ、フィガロンだけは青ざめていた。
ヴィオが生ぬるい微笑みを向けてくる。
「まあ…せいぜいエコーの堪忍袋の緒が切れない程度には健闘してくれ…それなりに、面白いから」
「ど、どういう意味?」
「あ、なんかその言い種ひどくなーい、ヴィオくん?」
「そうですか?」
「気のせいですわよ」
「へーえ?二人して僕の敵にまわるんだあ?」
エコーがにやりと笑う。対する二人は余裕の笑みを崩さない。
―仲がいいんだか悪いんだかさっぱり分からないな、この集団。
ダニエリンは心の中で呟いた。
そしてふと、いつの間にか温かい気持ちになっていることに気付く。
この四人の傍にいると、暗い過去を忘れていられる気がした。
そのことに罪悪感を感じながらも、このまままどろんでいたい、とダニエリンは思わずにはいられなかった。
三、煩いんだけど。